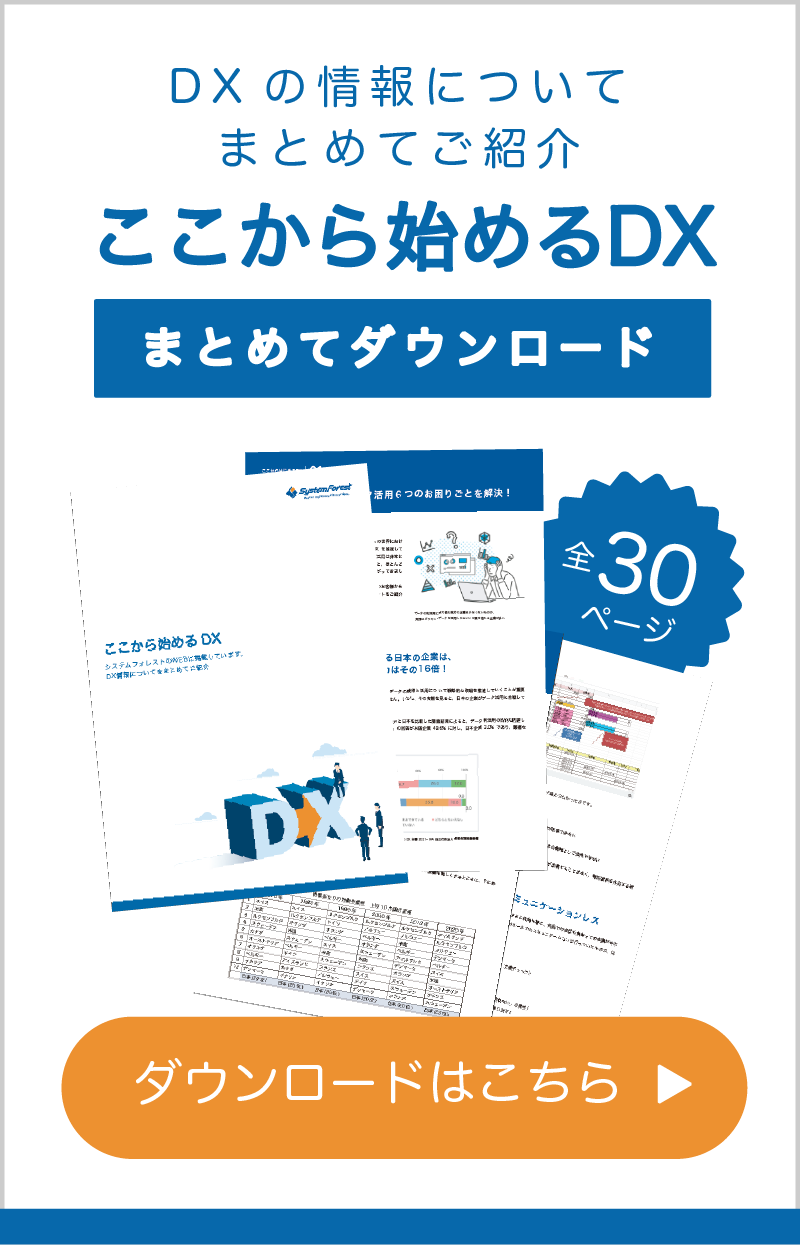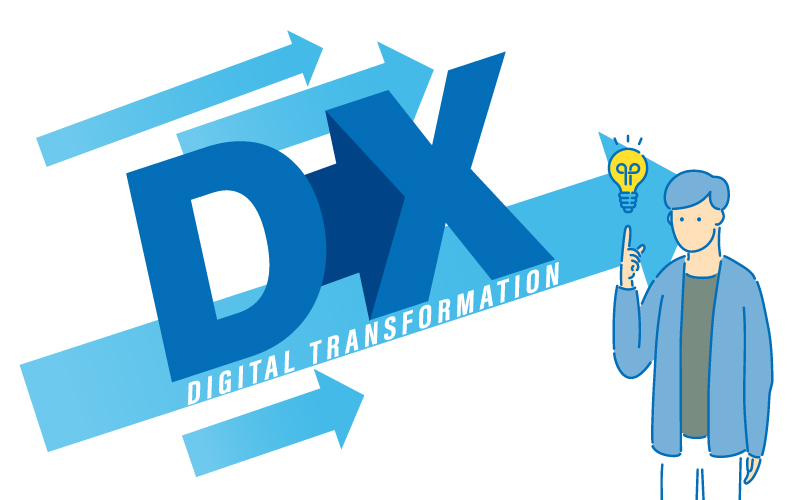
新型コロナウイルスによる経営や事業への影響が各業界に及ぶ中、各社でDX化への取り組み、それに伴うデジタル活用が急速に進んでいます。そして今やITは企業活動にとって重要な存在となりました。
日常業務でExcelやWordでの書類作成、メールの送受信、社内の稟議申請、Webサイトを活用した製品販売などさまざまな業務でITが使われているものの、未だにITを十分に活用できてないという事業者の声も少なくありません。
先日見かけたTikTokの動画では、就職活動を行っている学生向けに「紙資料文化の会社は遅れている」「メールと電話のコミュニケーションは時代遅れ」と就職すべきではない会社の特徴を発信していました。これから入社を希望する人材にとって、社内のIT化がどれだけ進んでいるかも重視される時代です。
IT化は大掛かりなシステムを導入し、パソコンを駆使して全社員が利用するイメージがありますが、もっと小さな課題を解決する簡単なシステムで始めることでも、IT化を大きく前進させることができます
自社に適したIT化の進め方とはどのようなものなのか、またなぜ企業がITを活用することが重要なのかなどについて事例を交えてご紹介していきます。
日本企業のIT化が遅れているのはなぜ?
一見技術革新を多く感じられる日本ですが、大半はITを十分に活用できない、またはそもそもITを導入していないという企業が実は多くを占めています。日常業務でパソコンを利用しているにも関わらず、提出は紙資料だったり、社員間での共有も未だに閲覧用ファイルで回したりと、まだまだアナログでのやりとりが多く発生しているのではないでしょうか。ではなぜビジネスにおいてなかなかIT化が進まないのか。理由を探っていくと環境やその思考に原因がありました。
原因その1:ITに対する理解不足
日本は、他の先進国に比べてITに対する理解が不足していると言われています。というのも新技術や新しい概念に関するドキュメントは英語で公開されることが多いため、新しい技術をキャッチアップするためには英語力は欠かせません。システムを見た途端に苦手として捉えてしまうのは、日本は義務教育などで英語を取り入れてはいるものの、英語を実際に使えたりドキュメントを読みこなせる人材が少ないことが影響しています。
原因その2:お客様思考が強い
日本企業は他国と比較しても、サービスの質が非常に高いと言われています。対応品質の高さはお客様に対する大きな価値ではありますが、目の前のお客様のとっての価値となっているか?」がとても重要です。
システムの開発に関してもそれは同様であり、実は弊社も以前はそのような受託開発を中心に行っておりました。
基本的に受託した側(システム会社)はクライアントの要望に沿って仕様を決める必要があります。しかしクライアントの言われるがままにシステムの開発を進めたことで、場合によっては使いこなせなかったというケースもありました。
受託側がうまく説得できればよいのですが、「お客様指向」が強すぎるとそうもいきません。結果、目先の業務は効率化できるものの、機能過多になってしまったり、拡張性やメンテナンスがしづらいシステムが開発されることになりかねません。
原因その3:IT化を進めにくい環境
日本企業の雇用形態は終身制であり、一度雇った社員は定年まで会社が面倒を見るという風土が根強く残っています。であれば、会社組織としてもそれを前提に社員教育を施す必要があり、それがITスキルの枯渇化に繋がっていると指摘されている面もあります。昔から勤務する社員の業務の手法が優先されるがゆえに、今なお紙資料でのやりとりが中心であります。
一方米国などでは転職をして自身の専門的なスキルアップを図ることが前提の雇用形態です。そのため日々新しい人材が新しい手法を取り入れ、業務効率を挙げているため、IT化を進めるにはもってこいの環境と言えます。
一つの組織で定年まで幅広くやっていくのでは人材の育ち方に違いが出るのも当然と言えるでしょう。特化した人材を育てるためには前者の方が有利になるため、日本企業の雇用制度とIT人材の育成は相性が悪いと言えるのではないでしょうか。
また中小企業におけるITの導入が一向に進まないのは、費用がかけれない、効果が見えない、ITスキル・人材不足、自社に合ったツールではないと理由は様々出てきますが、そもそもこれまでの組織文化なども影響してIT化への障壁が高く、身近な使えるツールとして捉えていない、どう使えるかわからない、といったことが最大の障害となっていることが多く見受けられます。
IT化に潜む落とし穴
IT化が進んでない、大企業しかなかなかIT化に取り組めれない・・、そのような考えをお持ちの経営者も多いのではないのでしょうか。IT人材が豊富とは言えない国内においては、身近にITについて相談できる社員が不足しているがゆえに会社に最適なITツールを選択し、使いこなすということはハードルが高いと言わざるを得ません。そのため自社がこれから目指す姿や経営戦略に沿ったIT戦略の立案、また高度なIT活用を行うことは非常に困難です。
実際に「高価なシステムを入れたものの、結局、集計と帳票の印刷程度しか使っていない」「組織の活性化のために有名なグループウェアを導入したがまったく効果が出ない」「入力が面倒なので社員はほとんど見ていない」などはよく聞く話です。
これらは解決したい課題が明確でない、または問題全てを一気に解決することに取り組んだために「アレもコレも」と欲張ったシステムを導入してしまう、つまり、導入すること自体が目的となってしまい、本来解決すべき課題が置き去りになっていることに起因していると言えるのではないでしょうか。課題が明確でなければ的外れなIT活用になり、結果的に導入しても無駄になってしまいます。
ITは手段であって万能薬ではありません。自社に適したシステムでなければ活用しきれないだけでなく、コスト面でも導入にかかる労力の面でも無駄な投資になってしまいます。重要なのはあくまでも自社の経営戦略に基づいてビジョンや目標実現のための手段としてITを使いこなすことです。
自社に適したIT化の第一歩は最小限からまず始めること
また、結果を出すIT化の手始めは、効果が目に見えるところから始めるべきです。例えば、社員間でのコミュニケーションツールなどは全社員が関わっており、効率化の効果が見えやすいでしょう。今は私生活でもチャットやSNSを中心にやり取りする機会が増えてきたので、仕事でも利用したいと思う社員も増えています。また月々のライセンス費用が発生するシステムとはいえ、手頃な値段でシステムに触れる機会が生まれます。
次に手作業により紙やエクセル管理で行う業務の効率化を見直すのはいかがでしょうか。紙の方がシステムに比べて入力の手間や操作が分からないこともないので管理しやすいと思われがちですが、上長への申請・承認、その後の数字のチェックや仕訳、ファイルでの保管までをすべて手作業で行うことになります。紙で管理している業務をIT化すれば、一つ情報を入力するだけで金額等が自動計算される他、仕訳作業やデータ発行、さらには分析も自動化できます。IT化で一元管理できるようになれば、作業時間や手間を省くことができる上、ペーパーレス化によるコスト削減にもつながるでしょう。
これまで自社で開発したシステムを利用していた企業にとって、クラウドサービスのように月々の金額が発生することに抵抗のある方も多いです。しかし自社開発のシステムに比べて初期投資を低く始められ、自社に合わなければ別のものに切り替えるというメリットもあります。こうして試しながらシステムを運用していき、複数の選択肢から自社の事情にあったところを選択できることが、クラウドサービスやライセンス型のサービスの大きなメリットです。
企業のIT活用事例
事例1 城北自動車学校様
 城北自動車学校様では大きな課題の一つに、生徒に乗車日時を連絡することの難しさがありました。 指導員からの連絡に生徒が返信をしても学科や実技指導中であれば電話に出ることができません。また一度のやり取りで連絡を終えることは ほとんどなく、さらに担当している生徒数が20人近くに上るため、連絡のために休憩時間や食事の時間も満足にとることができないなど、現場の指導員にとって大きな負担になっていました。 そこへチャットサービスを導入したことにより、生徒への連絡に苦労していた指導員も情報伝達がスムーズになり、気持ちにゆとりがもてるようになりま した。また緊急時に社員同士の連絡がスムーズにいくことも効率化に繋がりました。
城北自動車学校様では大きな課題の一つに、生徒に乗車日時を連絡することの難しさがありました。 指導員からの連絡に生徒が返信をしても学科や実技指導中であれば電話に出ることができません。また一度のやり取りで連絡を終えることは ほとんどなく、さらに担当している生徒数が20人近くに上るため、連絡のために休憩時間や食事の時間も満足にとることができないなど、現場の指導員にとって大きな負担になっていました。 そこへチャットサービスを導入したことにより、生徒への連絡に苦労していた指導員も情報伝達がスムーズになり、気持ちにゆとりがもてるようになりま した。また緊急時に社員同士の連絡がスムーズにいくことも効率化に繋がりました。事例2 KMバイオロジクス株式会社様

そこで自社でもカスタマイズが簡単に行えるシステムに切り替えたことにより、社員ニーズを組み込みながら最小限必要な入力項目を配置し、入力もリアルタイムに行えることに対応したことで、上司が部下の状況を素早く確認できるようになったという事例です。
他にも多くのお客様でそれぞれ異なる業種業態でITを活用した成果をご紹介しております。
その他事例をご覧になりたい場合はこちらから!ぜひ御覧ください